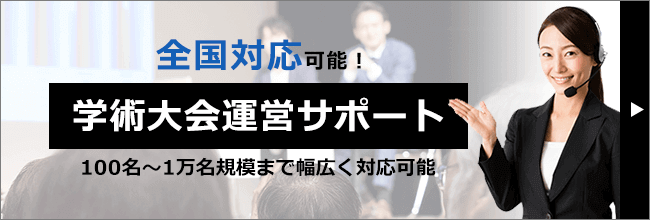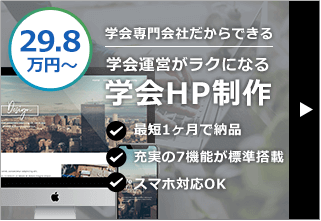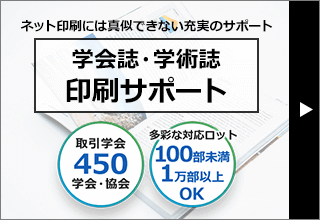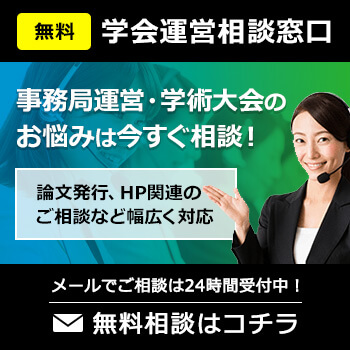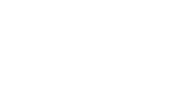学会の税務にも必要? インボイス制度とは
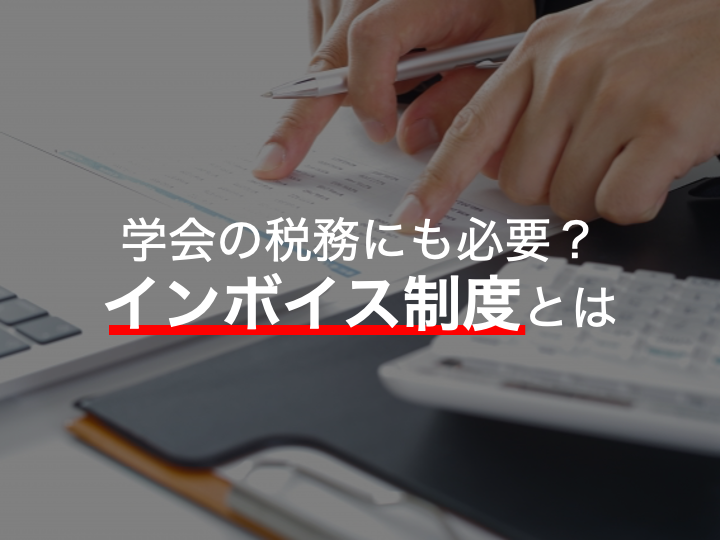
2023年10月より、消費税の控除に関連する「インボイス制度」が導入されます。
今回は、インボイス制度導入にあたり学会がおさえておくべき事項について詳しく解説いたします!
(記事の内容は2022年10月時点の情報をもとに制作しています)
インボイス制度とは
適格請求書(インボイス)とは?
適格請求書(インボイス)とは、通常の請求書に加え登録番号や提要税率を記載したものです。
従来の請求書には以下の事項が記載されます。
・請求書発行事業者の氏名 / 名称
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとに区分して合計した対価の額
・交付を受ける事業者の氏名 / 名称
インボイスには、通常の請求書に加えて以下の事項を記載します。
・発行業者の登録番号
・適用される税率
・税率ごとの消費税の合計額
インボイス=適用税率と登録番号を記載した請求書
と、認識しておきましょう。
消費税控除のため制度化
インボイス制度とは、事業者が消費税の控除(仕入税額控除)を申請する際に、取り引き先が発行するインボイスの保存を義務付けるものです。
日本では2023年10月より制度が施行されます。
消費税控除にインボイスが必要となるため、企業が取り引き先にインボイス発行を求める機会も増えるでしょう。
では、学会はインボイスの発行をすべきなのか。
次節では学会のインボイス発行について解説します!
学会税務にインボイスは必要?
消費税が課される場合に必要!
学会がインボイス発行をする必要があるのは、外部の事業者との取り引きに消費税が課税される場合です。
取り引き先の事業者は学会が発行するインボイスがないと、消費税の控除が受けられません。
しかしながら、一般的な学会運営における会費や大会参加費は不課税とみなされるため、インボイスの発行も必要ありません。
そもそも、消費税の課税対象は「対価性」のある取引です。この取り引きは商品やサービスの対価として報酬を受け取るものを指します。
一方で、学会運営に必要な会費の徴収や、会員に向けた大会参加費の徴収には消費税が課されません。会費や大会参加費は直接的な対価とは見なさないケースが多いからです。
しかし、一部の取り引きには対価性があると見なされ、消費税の課税義務が発生します。
次節ではその取引について解説します。
学会の活動が消費税課税の対象となる場合
学会の活動の中で、以下のような取り引きを行った場合消費税の課税義務が発生します。
・書籍販売や広告収入など、明確な「対価性」のある取り引きを行う場合
学会から書籍や広告による収入、企業からの研究事業の請け負いなどを行う学会もあるでしょう。
そのようなケースでは、明確な対価性があると見なされ消費税の課税対象となります。
取り引き先も企業であることが多いため、インボイス発行を検討すべきでしょう。
・学術大会や研修の参加費を「非会員」から徴収している場合
大会や研修の参加費を会員から受け取る場合、その金銭はあくまでも学会の活動のために使われるとみなされ、消費税は不加税となります。
一方で、非会員から参加費を徴収する場合は対価性が発生してしまいます。大会や研修といった「サービス」を提供することで、利益を得ていると見なされるためです。
特に、企業から参加費を徴収する場合には注意が必要です。
企業は消費税控除のために、インボイスを交付するよう要求される可能性があります。
学会活動の課税についての関連記事としてこちらもご参照ください。
学会の参加費に消費税はかかる? | SOUBUN.COM
インボイス導入のメリット / デメリット
インボイス導入のメリットは「企業受けが良くなる」ことです。
企業は消費税控除を申請するため、インボイス発行を求めるようになるでしょう。
そのため、企業はインボイス発行が可能な学会を好む傾向が強まります。
企業との取り引きを行う学会はインボイス導入をおすすめします。
学会向けインボイス発行方法
インボイス発行には申請登録が必要
インボイスを発行するには、学会が「インボイス発行事業者」となる必要があります。
そのためには、税務署へインボイス発行事業者としての登録申請を行わなければなりません。
税務署への申請書類提出や、国が運営する税務システム「e-Tax」から登録が可能です。
登録完了後、事業主に「登録番号」が割り当てられます。
2023年10月からインボイス発行を行うためには、2023年の3月までに申請を完了させる必要があります。
必要事項を記載したインボイスを交付
前々節で解説したように、インボイスには通常の請求書に「登録番号」「適用される税率」
「税率ごとの消費税合計額」を記載します。
より詳しい記載事項は、国税庁HPや同庁が発行する以下のパンフレットをご覧ください。
(令和3年7月) 適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-
インボイス発行の注意点
学会はインボイス発行事業者となることで、消費税の納税義務が発生する「課税事業者」となります。
そのため、毎年3月の末日までに消費税を納める必要があります。
学会の税務が増えるため、学会の税務担当者と相談した上で発行を検討しましょう。
学会の税務はSOUBUN.COM
SOUBUN.COMは学会サポート会社として80年の歴史があります。
学術大会の運営や学会事務局代行など、様々なサービスで学会の負担を軽減します。
学会の会計事務局代行も承っております。
インボイスの発行にも対応したサービスを提供可能です。
詳しくはこちらをご覧の上お問い合わせください。