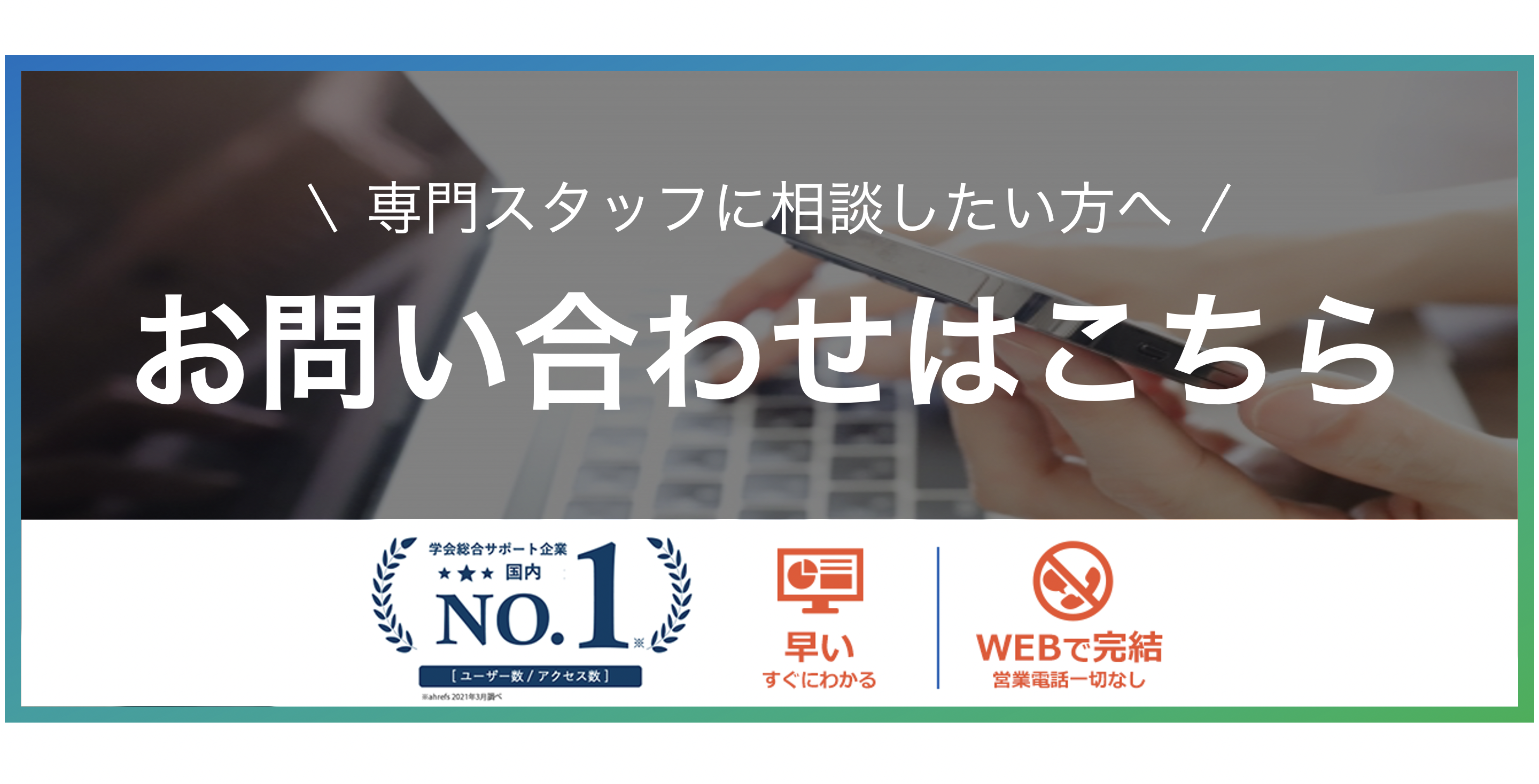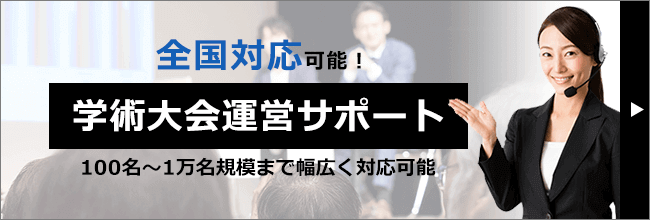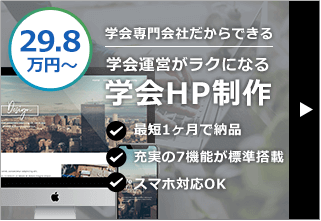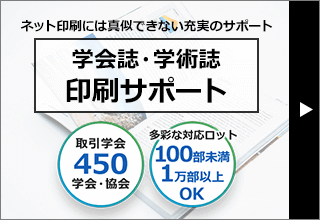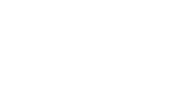学会への論文投稿方法や、投稿先の選び方

その分野において専門家が集まり、コミュニティを形成し、情報共有を行なっていく学会。
学会を通じて得られた知識は、社会貢献へ広めていく必要があります。
その情報公開の手段には学術大会や学会誌での論文発表があります。論文発表を考察し、その重要性を探っていきます。
論文投稿にあたっての要件
学会に所属するということは、その分野においてより専門的な知見や情報を得ることが目的のひとつです。学会を通じて得られた知識を広めていく必要があります。
研究成果を論文として発表し、外部から客観的評価を受けることも学会に所属する意義となります。
すでにある研究結果を基に、新たな知見を積み上げていく。または既存の結果を裏付けたり、関連させる。これらの研究が結果を有するならば、論文投稿の要件は十分となります。新たな知見の積み上げは原著となり、既存の裏付けは症例報告、エビデンスとなります。
論文投稿の準備
論文投稿にあたっては、まずその学会の投稿規程を確認します。学会が公開する論文投稿の手引きやガイドラインの閲覧をお願いいたします。
投稿規程には書式および記載項目、文字数や英文指定、別刷や投稿料などについて、記載がなされています。審査の厳しい学会では、字下げや1ページの行数等の書式が規程に沿っていないといったことでも、リジェクトされることがあります。また、発刊する号毎に締め切りも異なりますので、学位等に必要な場合には、ジャーナルの発刊や公開に間に合うよう、十分に余裕をもった投稿が必要となります。
また、学会によっては共著者も会員である必要がある場合があります。共著者の学会所属情報、非会員の場合には入会の手続きも必要となります。詳細については、学会の投稿規程および定款を確認しましょう。
投稿する学会のルールがわかれば、それに則り、研究結果をまとめていくことになります。
また、投稿前にそのジャーナルの採択率を確認するのもよいでしょう。
学会の採択率の調べ方については、こちらをご参照ください。
自筆論文の投稿先を見つけるのに役立つ採択率(アクセプト率)の調べ方
学会への論文投稿の流れ
論文を執筆したら投稿となります。以前は、投稿論文の原稿を3、4部プリントし、著者が学会事務局や編集事務局へ提出していました。現在では、エディタルマネージャーやスカラーワンなどの査読システムの利用や、学会HPからオンライン受付等も増えてきました。いずれの場合も「投稿票」や「チェック票」、「COIの申告」は必須となりますので、注意が必要です。
届いた書類の内容に過不足がなければ「受付」となります。学会側が論文を受け付けると、システムや担当者から受付の連絡が届くのが一般的ですので、数日間経っても連絡がない場合には、確認をすることをお願いいたします。
受付後に査読者が決定され、査読が開始されます。
学会によって異なりますが、1週間〜1か月程度で査読結果が届きます。「採用」なのか「修正後採用」なのか「修正後再判定」なのか「不採用」なのか、結果を確認し、査読コメントに従い内容の修正・変更を行い、再投稿を行います。これを繰り返し、掲載採用、つまり「受理」となり論文が公開されます。なお査読は指導ではないので、注意が必要です。
最近ではオンラインジャーナルの普及も後押しし、スピード感が求められますが、投稿から採用までに3か月程度かかる場合もありますので、掲載したい時期が決まっている場合には、余裕を持った投稿が必要です。
論文投稿の注意点
論文投稿には手続きが多く、その中で注意すべきポイントがあります。まずは時間です。掲載時期・公開時期の希望があるようであれば、余裕をもった対応が必要です。
次に修正において重要なのが、査読コメントへの返答です。お礼に始まり指摘に対し誠意あるコメントがあるものと、「修正しました」のみの返答では査読者の印象が大きく変わります。書き方で審査に影響がでることはありませんが、どのように直したのかが伝わらなければ、再質問を受けることになります。
すばらしい研究結果も報告しなければ意味がありません。そのためには、まずは投稿という第一歩が重要となります。学会毎に規程は運用が異なり、意図しない間違いを生むこともありますが、人類の未来のため、投稿が必要です。
論文投稿と学会発表の違い
研究成果を発表する際には、論文投稿以外に学会で発表する選択肢もあります。ここでは、学会発表の利点と注意点について解説いたします。
学会発表の利点
論文投稿と比較した際の学会発表のメリットは複数あります。
1つは、研究の途中段階でも発表できる点です。論文は研究が完成して投稿するものですが、学会では研究が完了していなくても発表することができます。そのため、発表後に他の研究者から質疑応答やコメントを受けることで、課題や新たな視点を得ることが期待できます。
また、学会発表は人脈の形成にも繋がります。学会は研究者や専門家が集まる場所であり、発表を通じて多くの研究者と関わる機会があります。その繋がりが共同研究や自身のキャリアアップに繋がるかもしれません。
加えて、発表スキルの向上もメリットの一つです。定期的に発表をすることで、論理的に要点を伝えるプレゼンテーションスキルを磨くことができます。
学会発表の注意点
学会発表における3つの注意点を解説いたします。
1つ目は、発表の事前準備です。発表練習を重ね、聞き手が短時間で内容を理解できるよう工夫し、時間内に発表を終えられるようにしましょう。学会発表に慣れていない場合は、教授や先輩の研究者に発表を見てもらうのも1つの手段です。
2つ目は、専門外の聞き手への配慮です。自身の研究領域では一般的な言葉も、他分野の研究者にとっては知らない言葉かもしれません。用語や概念の解説は、必ず入れるようにしましょう。
3つ目は、スライドやポスターのデザインです。文字のサイズやフォントを統一し、文字だけでなく図や画像も用いてわかりやすい発表資料を作成しましょう。スライド・ポスターのデザインについては、こちらの記事もご覧ください。
学会における発表スライドの作成方法 | SOUBUN.COM
学会発表(ポスターセッション)用ポスターの作り方ガイド | SOUBUN.COM
学会のことならSOUBUN.COM
SOUBUN.COMは、学会サポートの事業会社として80年の歴史があります。これまで、200を超える組織・団体とお取引させていただきました。
学会の活動をサポートする各種サービスをご案内しており、出版物の発行、J-stageの登録代行、学術大会や国際会議の運営代行、セミナーや講演会のサポートなどを行っております。
学会・学会誌のことでお困りのことがありましたら、下記のリンクよりぜひお気軽にお問い合わせください。