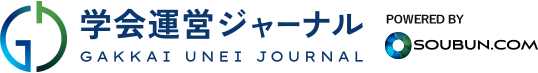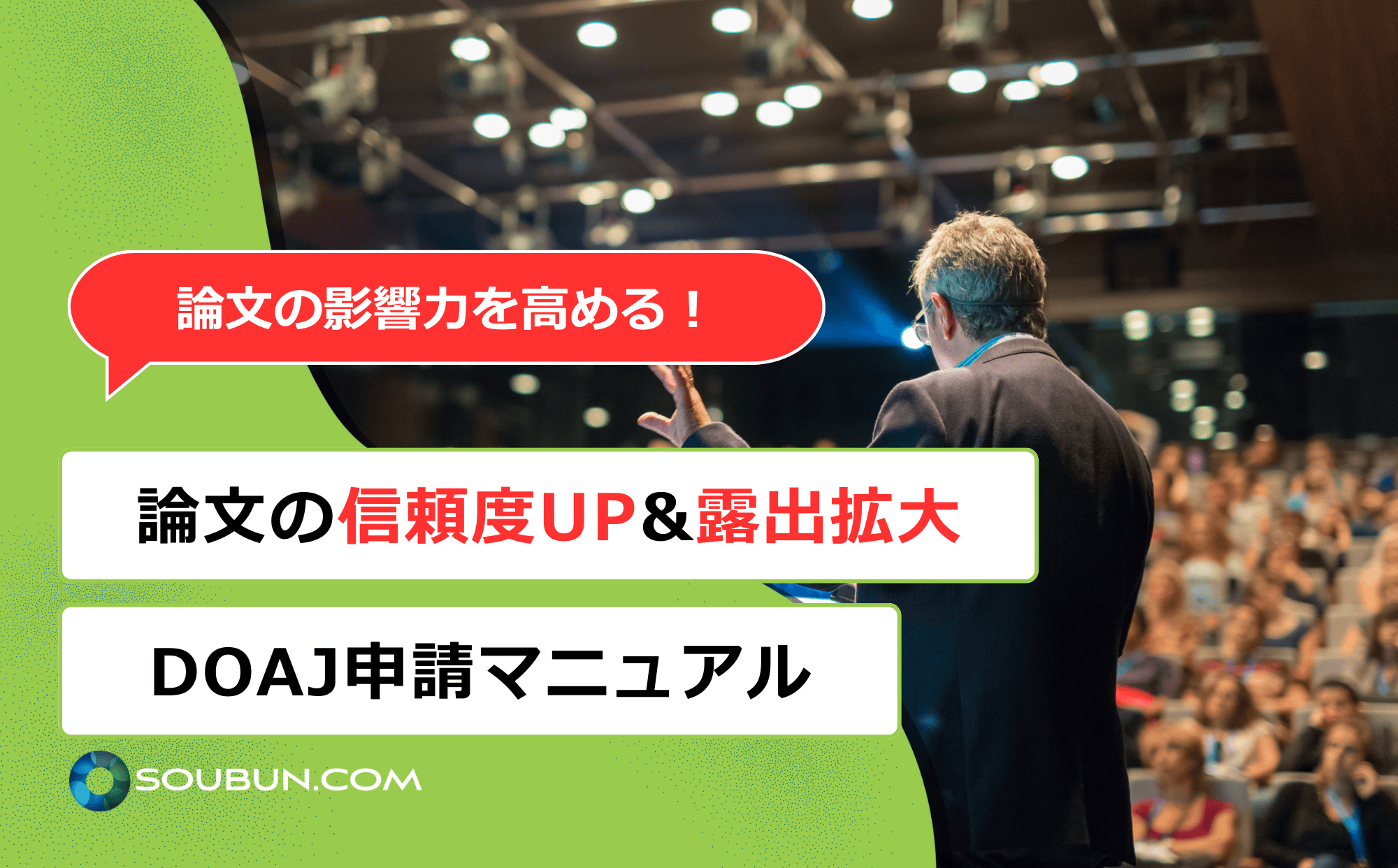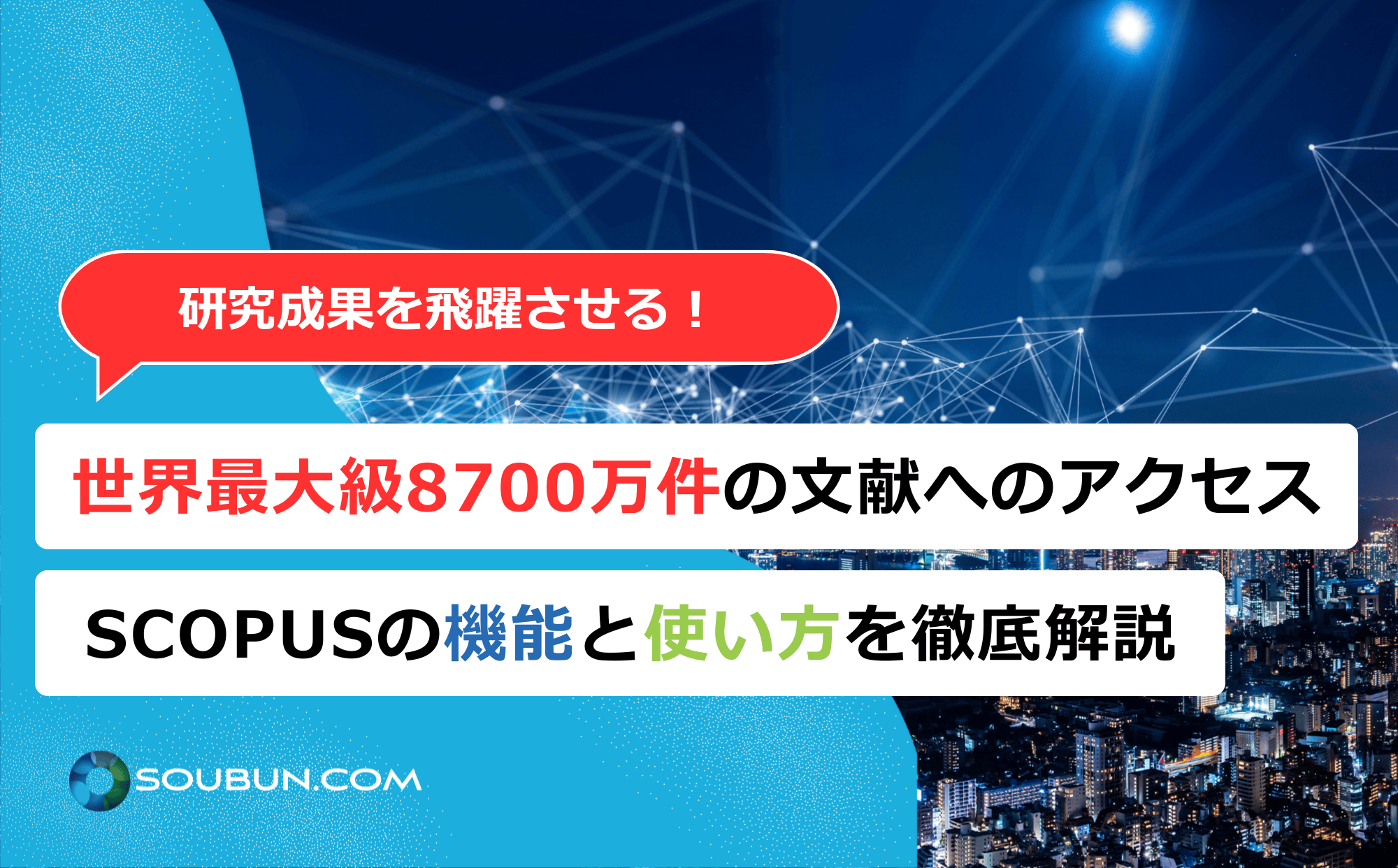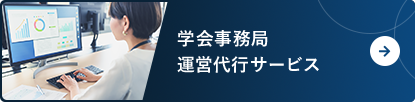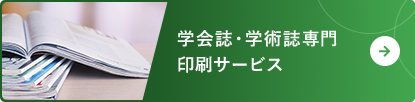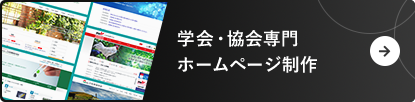学際的研究とは?:専門分野を超えた研究のメリットや課題

学際的研究の定義からメリット、具体的な研究事例、課題までをわかりやすく解説。異分野連携や異分野融合を理解し、専門分野を超えた新たな研究の可能性に触れてみましょう。
学際的研究の定義は?
専門分野を超えた学問領域
学際的研究(Interdisciplinary Research)は、「単独の学問だけでは解決が難しい課題や研究テーマに対して、複数の学問を連携・融合させ研究すること」と定義づけられています。問題をさまざまな視点から見つめることで、新たな解決策を見出すことが期待されます。
最近よく耳にする「SDGs(持続可能な開発目標)」に関する研究も学際的研究の1つ。人口減少や地球温暖化といった課題がある中で、経済学、環境科学、政治学、自然科学の研究者が協力して持続可能な社会を目指す研究が行われています。
異分野連携と異分野融合の違い
学際的研究は「異分野連携」と「異分野融合」に大別されています。しかし、「二つの違いがわからない」という声も多くあります。
まず異分野連携は、それぞれの研究者が専門とする学問の範疇で意見を出し合い、協力して課題を解決するものです。
それに対し異分野融合は、研究者が専門分野を超えて意見を出し合い、新たな研究テーマや手法を生み出し課題を解決するものです。
また、学際的研究とよく混同される言葉として、他分野が開発した技術を利用する「技術の借用」、新たな知見・手法の発見を目的としない「複合領域研究」などがあります。
学際的研究のメリットは?
知識と経験の共有
学際的研究の意義は、知識と経験の共有にあります。
現代では、学問が非常に細分化されており、それぞれの研究者が深い知識や専門的な技術を持っています。それがかえって研究者の専門分野への閉じこもりを促進させ、幅広い視野を持たなくなる危険性も生み出しています。
しかし、学際的研究を通じて知識と経験を異なる学問同士で共有することで、これまでにない観点から研究テーマを考えること、新たな実験方法を生み出すことが期待できるでしょう。
新たな学問や技術の創出
複数の専門家が協力することで異なる分野の知識や技術が統合され、新たな学問や技術が生まれることも学際的研究の利点です。なぜなら、学問の進展が促され、社会の発展にも繋がるからです。
例えば、政治学と経済学が融合した政治経済学により、過去の政策や国際貿易についてより詳細な分析が可能となりました。また、医学と工学が連携することで、新たな医療用検査機器が開発されています。
新たな学問や技術の発展を通じて、私たちの社会をより豊かにしてくれるでしょう。
複雑な問題へのアプローチ
複数の学問領域が協力することで新たな学問や手法を生み出し、より複雑な課題にも対処できるようになります。
先の例にも出した「SDGs」はその典型と言えるでしょう。持続可能な開発目標のテーマには環境保護や教育、貧困やジェンダー問題など多くの問題が複雑に絡まっています。この課題に対して1つの学問で解決しようとしても、そもそも解決の糸口が見えなかったり、解決しようとしても別の課題が発生してしまいます。
そこで複数の専門家が互いの知識や経験を共有することで、より効果的な解決策が見つかります。
学際的研究って具体的にはどんな研究?
情報学と翻訳研究
情報学と翻訳学の学際研究により、翻訳技術は飛躍的に進歩しています。
ある研究では、人工知能(AI)に大量の翻訳データを学習させています。AIは単語や文章をベクトルとしてとらえることで、単純な逐語訳ではない自然な翻訳を実現しています。
この技術は現在も進化を続けており、今後どのような翻訳システムが生まれるか、非常に待ち遠しく感じます。
地球温暖化問題の研究
地球温暖化問題については、多くの学問が連携しながら解決方法を模索しています。環境問題に関わるプロジェクトに関心を持つ研究者が集まり、それぞれ専門の視点を持ち寄ることで、問題の本質を深く理解し、解決策の構築に取り組んでいます。
例えば、気象学者は気候のメカニズムから将来の気候変動を予測します。それに対し環境学者や生態学者は、気候変動の影響が地球に住む動植物にどのような影響があるかを考えます。また、経済学者や政治学者は最悪の未来を回避するためにどのような政策や制度を用いるべきか考えるでしょう。
地球温暖化は多くの分野に影響を及ぼす複雑な問題であり、解決には各分野の専門家が協力することが必要になっています。
歴史学の学際研究
歴史学は他の学問との融合・連携を繰り返し、進化してきた学問です。
例えば、考古学が持つ遺跡や遺物の発掘技術や、遺跡や遺物を解釈する際の考古学的知見は、歴史的資料の発掘とその解釈に役立ちます。他にも、地理学と連携した過去の地形分析、研究生物学と連携した古代DNAの分析、言語学と連携した古文書の解析など、多くの研究者を巻き込み進化していることがわかります。
歴史学は多くの学問の知見を積極的に取り入れています。学際的研究を進める際の手本としてはいかがでしょうか?
学際的研究の課題は?
上記のメリットから、学際的研究は非常に魅力的に感じるかもしれません。しかし、学際的研究にはさまざまな視点から認識される課題も存在します。
コミュニケーションが難しい
学際的研究にはいくつか課題があります。その1つは、コミュニケーションに関わるものです。研究者はそれぞれの専門領域については詳しい一方、他の分野については門外漢です。それ故、専門用語が通じない、研究手法の差異などの理由からコミュニケーションが取りずらいケースも多々あるようです。
この課題を解決するためには、なるべく専門用語を使わず、他の学問を尊重する態度をとり、お互いを信頼し合うコミュニケーションが重要となります。
専門性の向上と他分野からの学びのバランス
学際的研究においては、自らの領域における研究内容や手法を客観視した上で、新たなアイディアや方法を積極的に取り入れる必要があります。このバランスが難しく、専門性ばかり極めれば視野が狭くなり、他分野からの吸収ばかりでは専門性がなくなってしまいます。
専門分野と他分野の距離を適切に保ちつつ、様々な観点から研究ができる研究者を目指しましょう。
学際的研究の進め方
複数分野の研究者との連携
学際的研究を始めるには、まず他分野の研究者に共同研究の申し出、プロジェクトの提案を行う必要があります。知り合いの研究者から紹介してもらう、論文をチェックし著者に連絡する、他分野の学会・協会に参加するなどしてみましょう。
また、チームを結成した後のコミュニケーションにも注意しましょう。先にも述べたように、専門用語を使いすぎず、他分野の研究者を尊重し、積極的な交流を図ることをおすすめいたします。
異分野の知識と理解の深め方
異分野の知識を取り入れ理解を深めるもっとも簡単な方法として、実際にその分野の専門家に話を聞くことをお勧めします。自分がわからない内容やより詳細に知りたい情報について、より深い理解とこれまでの経験をもって答えてくれるでしょう。
もちろん、その分野に関連する論文や書籍を読むことも大切です。また、「参考になる論文や書籍は何かある?」と、他分野の専門家に聞くのもよいでしょう。
プロジェクトマネジメントが重要
学際的研究ではプロジェクトマネジメントが重要です。
学際的研究は異なる分野からの視点を統合するという困難を伴い、意見のすり合わせや進行管理に時間をかけることは避けられません。
そのため、プロジェクトのリーダーが各分野の意見をまとめ、論点を洗い出し、方向性を定めることが大切です。また、具体的な計画の作成とスケジュール管理をし、定期的な情報共有も行いましょう。プロジェクトマネジメントの質が高ければ、学際的研究は多様な視点の結集と革新的な発見の場となるでしょう。
日本における学際的研究の現状と展望
評価基準の確立が望まれる
学際的研究の多くはその学問が誕生してから日が浅く、評価基準が明確ではない、もしくは評価基準が学際的研究に適していないものもあります。
例えば2022年に政府が発表した国際卓越研究大学の認定制度を見てみましょう。
国際卓越大とは、国際的な競争力の高いと政府が認めた大学です。その認定制度は以下のようなものです。
・各分野のTOP10%の評価を受ける論文が、大学の総論文数の1割以上である
・各分野のTOP10%の評価を受ける論文を、研究者1人当たり約0.6本以上執筆している
一方、学際的研究の一部は「各分野」に含まれないこともあり、また「TOP10%」の評価を比較することも難しいのが現状です。
学際的研究を促進させる上で、学際的研究を評価する仕組み作りが重要です。
若手研究者への支援も大切
学際的研究を促進する上で、重要なことの1つに若い研究者へのサポートがあります。分野に囚われない学際的研究は1つの視点から評価することが難しく、評価基準が定まっていないこともあります。それ故、若い研究者は既にある研究分野に収まることが多い、という意見もあります。
また、学際的研究のハードルの高さも若手研究者が苦労する要因の1つです。同じ分野での共同研究と異なり、学際的研究では最初の課題・仮説設定の段階から異分野同士の意見を擦り合わせなければなりません。その中で、年齢が若くチームをまとめられない、実績が少なくなかなか意見が信用されない、といった悩みも想定されます。
このような現状を踏まえ、政府や大学、学会や先輩の研究者は、学際的研究に臨む若手研究者を積極的にサポートすることが望ましいでしょう。
学際的研究に関わる大学の取り組み
東京大学の取り組み
東京大学は2019年に「東京大学未来ビジョン研究センター」を立ち上げました。同センターは社会課題の解決と持続可能性を目標として掲げ、超長期未来のビジョン形成、ビジョン実現のための協働研究、ビジョン実現のための協働研究を実施しています。実際にAIやヘルスケア、環境問題など日本の未来に関わる政策提言も行っており、学際的を促進する日本の最先端研究施設の1つと言えるでしょう。
京都大学の取り組み
京都大学は学際的研究の推進に力を注いでいます。例えば、「京都大学学際融合教育研究推進センター」では研究分野の融合・専門外での研鑽を軸に、学際的研究の運営支援や体制整備を行っています。また、「分野横断プラットフォーム構築事業」では、学祭的な研究集会やイベント企画へ支援を行い、異なる分野の研究者同士が交流する機会を設けています。
大阪大学の取り組み
大阪大学は大阪・関西万博の開催に向けて「大阪大学2025年日本国際博覧会推進委員会」を設立し、学際的研究の推進を行っています。委員会内には「いのち部会」、「先端技術体験部会」、「学生部会」、「国際部会」があり、各部会の異なるアプローチを通じて学際的なチャレンジを支援しています。例えば、「いのち部会」はSDGsの達成に向けて市民と対話し、それぞれが何をすべきかをアジェンダとして世界に発信しています。また、「先端技術体験部会」は学内の研究成果を用いて先端技術の体験を提供し、産業界との連携を強化しています。
学会・協会運営のことならSOUBUN.COM
学際的研究を通じて複数の専門家が協力することで、新しい知見や手法を生み出し、より発展した研究や技術に繋がるかと思います。
SOUBUN.COMは、学会・協会運営の手間やリスクを削減するサービスを提供しています。
事務局代行やHPの制作、学術大会やイベントの運営、学会誌の印刷など幅広いサービスを提供しています。
学会・協会に関するお悩みがありましたら、お気軽にお問合せください。